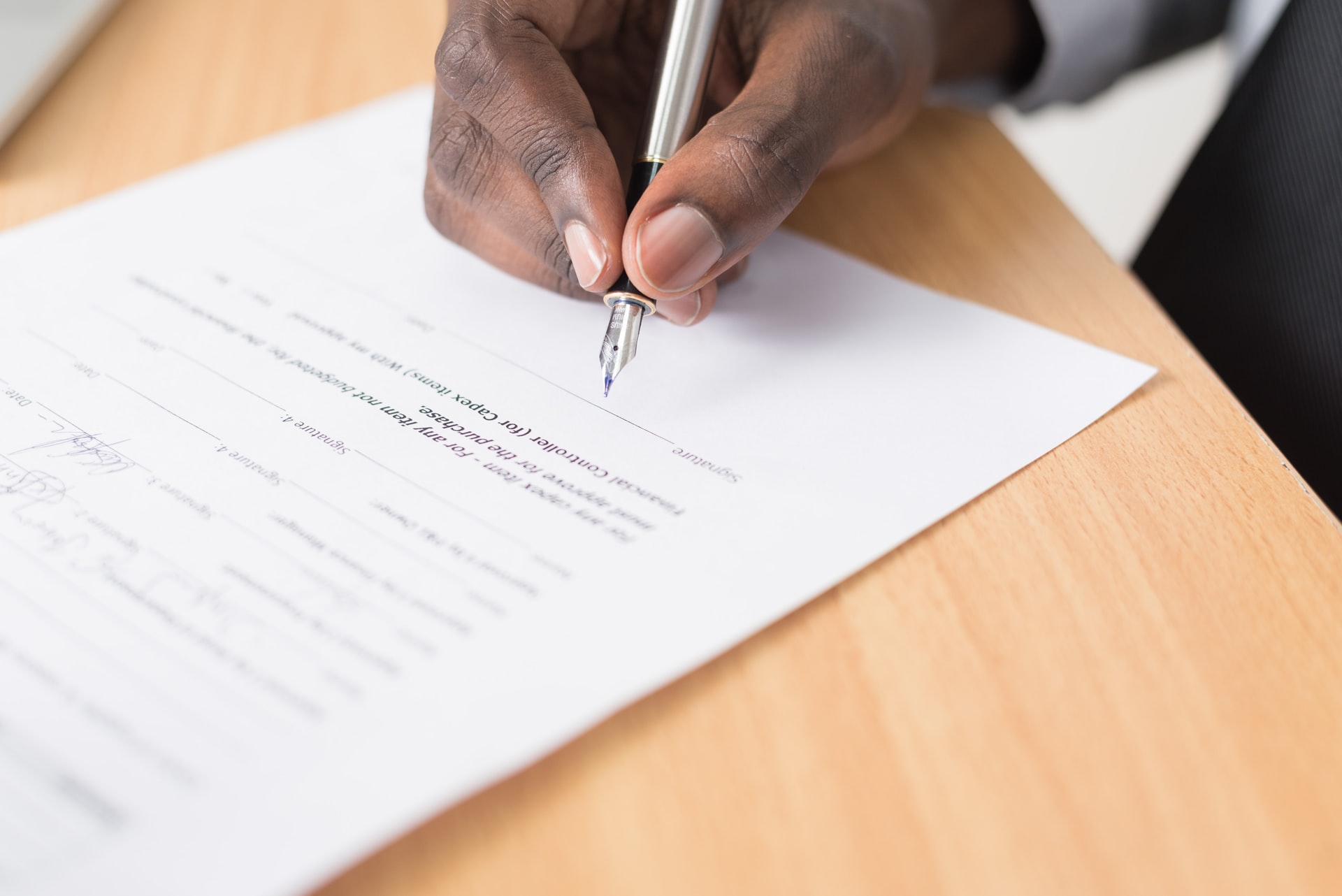【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労使協定(36協定)】
こんなお悩み抱えていませんか?
- 毎日サービス残業ばかりだな
- こんな残業して法律に引っかかってないのかな?
- 自分のためにも労働法について学びたい
こんな方は、社労士試験の勉強をしてみてはいかがでしょうか。
社労士は、労働社会保険諸法令に精通する唯一の国家資格になります。
勉強をすれば、自分の会社がきちんと労務管理をしてくれているのかがわかるはずです。
「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士が実務でも役立つ知識を、社労士試験の学習範囲に沿って解説するブログです。
今回は、「労使協定(36協定)」について解説します。
残業って何時間でもさせることができるの?

使用者は、労働者を法定労働時間を超えて労働させることは原則できません。
ただ、労基法36条の規定に基づく労使協定を締結し、その協定書を行政官庁に届け出ることで、延長することが可能になります。
延長できる限度時間について、次のように定められています。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
延長できる時間をまとめると、次の表になります。
| 原則 | 36協定による効果 |
|---|---|
時間外労働・休日労働禁止
|
時間外労働・休日労働可能(免罰効果)
|
36協定により、原則の時間を超えて、1ヶ月45時間、年間で360時間まで労働させることができます。
ちなみに、こちらの時間には、休日労働を含まないことは覚えておきましょう。
注意が必要なのが、表のかっこ書きの42時間と320時間の部分です。
これは「1年単位の変形労働時間制」を採用し、3ヶ月を超える対象期間定めた場合の上限になります。
変形労働時間制は、労働時間を短縮するのが目的のため、延長できる時間をより制限を掛けています。
「1年単位の変形労働時間制」を採用しているのに、採用していない場合の限度時間に誤って設定しないように、注意してください。
「変形労働時間制ってなに?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【変形労働時間制】」をどうぞ!

また36協定には、法定労働時間を超えて労働させても、使用者に労基法上の罰則が適用されなくなる「免罰効果」があるのみです。
36協定を締結させたからと言って、労働者に残業を強制できるものではありません。
労働者が所定労働時間を超えて労働する義務は、「雇用契約」や「就業規則」の定めによります。
つまり、「雇用契約」や「就業規則」で、36協定の範囲内で一定の業務上の事由があり、労働時間を延長して労働させることがある旨の定めがあれば、労働者は上長からの残業命令に従う義務を負います。
関連の判例として、「日立製作所武蔵工場事件」に目を通しておくといいでしょう。
《参考元》労働基準判例検索-全情報
続いては、36協定に定めておく必要がある事項を確認しましょう。
必要な協定事項
- 時間外又は休日労働できる労働者の範囲
- 対象期間(1年間限定)
- 時間外又は休日労働をさせることができる場合
- 対象期間における「1日」「1箇月」及び「1年」についての時間外労働又は休日労働の日数
- 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために、必要な事項として厚生労働省令で定める事項
対象期間とは、「時間外労働」「休日労働」をさせることができる期間をいい、1年間で設定する必要があります。
1年未満に設定することができない点は押さえておきましょう。
36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がありますが、営業所が全国に複数ある場合、すべての労基署に届出が必要なのでしょうか。
手間が省ける労使協定の本社一括届出とは?

労使協定は、事業所単位で、管轄する所轄労働基準監督署長に届け出るのが原則です。
そのため、営業所が複数ある企業にとっては、物凄い手間がかかる作業です。
ただ、そういった手間を考慮して、次のすべての条件を満たすことで、各事業所の36協定を、本社所轄の労働基準監督署長に、一括して届け出ることができます。
- 各事業所の過半数で組織する労働組合が本社と同一であること
- 本社と協定の内容が同一であること
- 本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含む事業所数に対応した部数の協定を提出すること
一括で届け出ることで、本社管轄の労働基準監督署長経由で、他の事業所の労働基準監督署長に届け出がされる形になります。
各所轄の労基署への提出手間が省けますので、実務担当者は覚えておきたい手続きでしょう。
36協定については、労務管理の担当者でしたら、必ず必要となる知識になります。
この機会に、手続き方法も含めて覚えるようにしましょう。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!