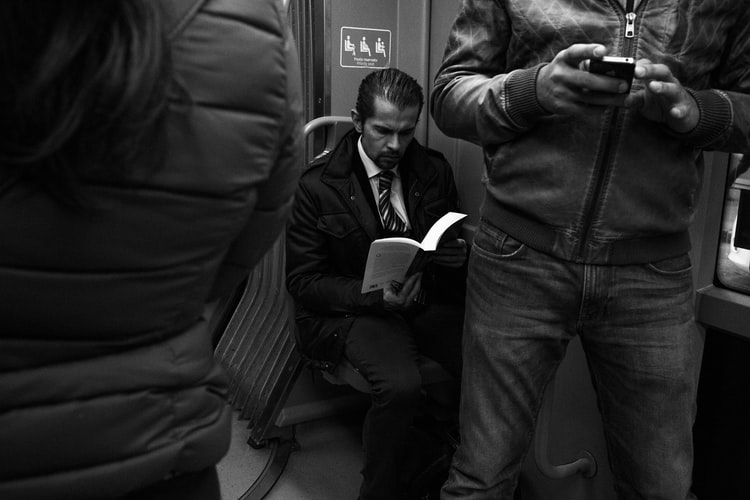【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働者編】
社労士受験の初学者の方にとっては、まだ社労士ってどんな仕事をしているのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
この「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役社労士である著者が「アガルート速習カリキュラム」で学んだ知識を基に、実務でも役立つ情報を発信するブログです。
勉強を途中であきらめるリスクが、少しでも減る内容にできればと思っています。
今回は「労働者編」です。
インターンシップの学生も労働者に該当するのか?

労基法が保護すべき「労働者」なのかを判断するのは、実務的にも非常に重要です。
「労働者」に該当するかどうかで、保護の程度が全く異なるためです。
労基法では、「労働者」の定義として次のように規定されています。
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「事業に使用される者」かというのは、雇用契約や請負契約などの形式ではなく、「使用従属関係」が認められるかどうかなど、実態によって判断されます。
では、インターンシップで実習に来る学生等は、「労働者」に該当するのでしょうか。
ここでも使用者と学生の間で、「使用従属関係」が認められるか否かで判断されるという、行政通達が出されています。
労働者と認められない場合
労働者と認められる場合
例え、夏休みの間だけ実習に来た学生であっても、「使用従属関係」認められれば、「労働者」に該当する可能性があることを覚えておきましょう。
また社労士の試験科目である「労災法」では、「労働者」を定義づけた条文はなく、労基法上の「労働者」と同義であるとみなされます。
つまり、第9条に「労働者」に該当する場合は、労災法の休業補償などの保護を受ける「労働者」になり得ることも、覚えておくと実務でも役立ちでしょう。
関連の判例としては、こちらの「関西医科大学研修医事件」も参考になると思います。
《参考元》労働基準判例検索-全情報
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!