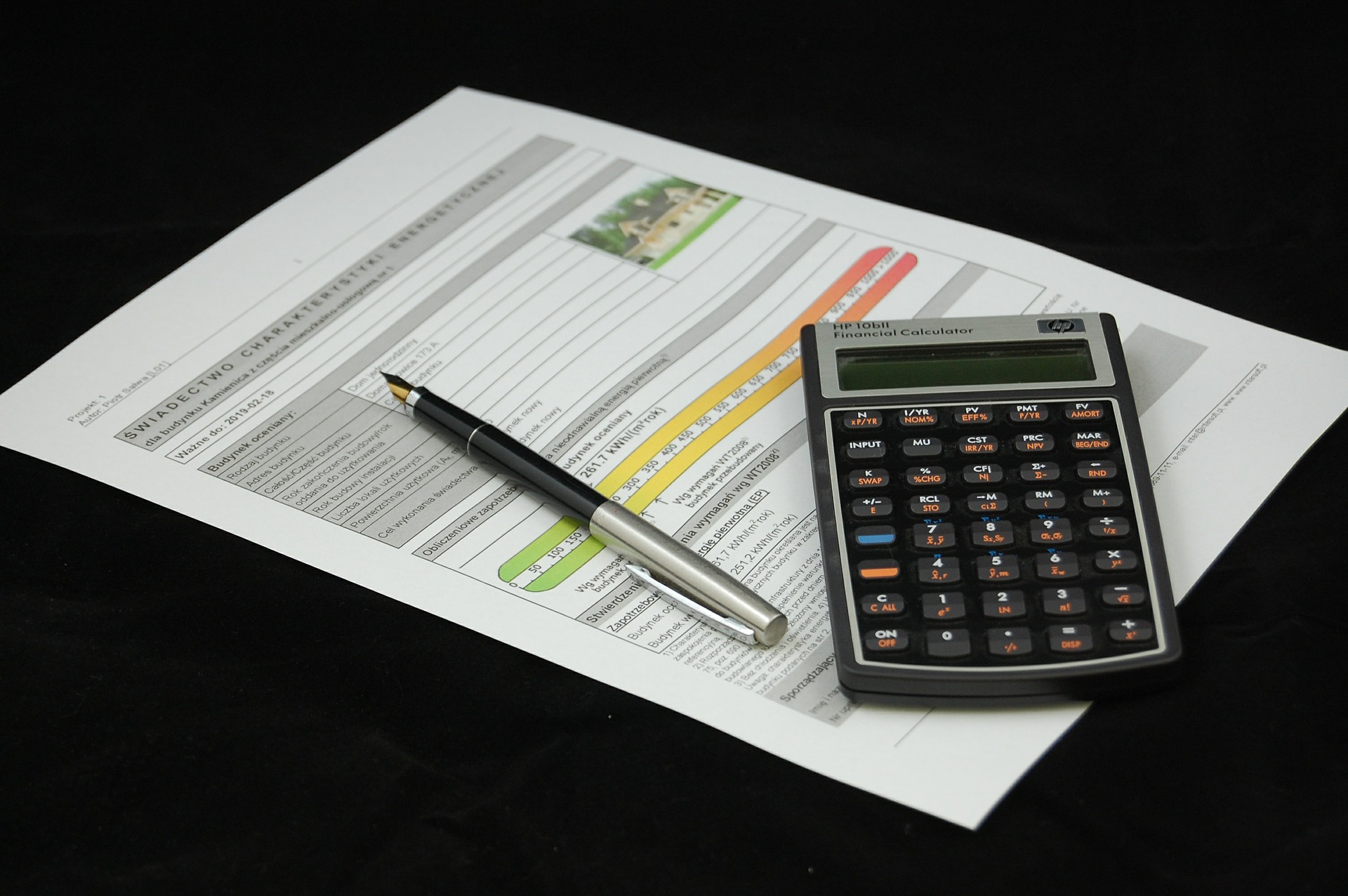【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【退職時の証明編】
社労士を目指す方は、普段働いている方が大半ではないでしょうか。
仕事を辞めて社労士試験に専念するという方もいますが、あまりおすすめできません。
それは、社労士試験が普段働きながらでも、十分合格が可能な試験だからです。
安定した収入がある中で、受験勉強する方が精神的に安定するので、いい結果が出やすい傾向にあります。
こちらの「ヤムチャ総務課長ブログ」では、初学者の方でもわかりやすいように、現役の社労士が実務に役立つ知識を解説しています。
仕事のちょっとした空き時間などに見て頂ければ幸いです。
今回の学習内容は、「退職時の証明と返還」になります。
退職した労働者に退職時等の証明書を求められたら何を書けばいいの?

労基法第22条では、「退職時等の証明」について、次のように規定されています。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
本条は、使用者と労働者の退職をめぐる紛争を未然に防止し、労働者の再就職活動に資する目的で、労働者からの請求があれば、退職時等の証明書を交付することを義務付けてます。
1項では、その証明する事項を、2項では法20条の規定により解雇予告をされた労働者についても、解雇が成立する日までの間、使用者に解雇の理由についての証明書を交付するよう定めています。
「解雇予告ってなに?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【解雇予告編】」のコラムをご覧ください。

またこちらの請求には、労働者の請求しない事項に関しては記入してはいけません。
使用者に証明を義務付けている事項は、次の表でまとめています。
退職時等の証明事項まとめ
| 退職した労働者 | 解雇予告を受けた労働者 |
|---|---|
|
|
これ以外の事項の請求があっても、使用者は交付する義務はありませんが、差し支えなければ交付してあげるようにしましょう。
また退職時等の証明書は、退職後何回でも請求ができますが、請求できるのは退職時から2年間とされています。
「解雇の理由」に関しては、就業規則のどの条項に該当して解雇するのかなど、その内容や事実関係を細かく記入する必要があります。
もし労使間で見解の相違がある場合は、使用者は自らの見解を示せばいいことになっています。
また4項の規定は、次の4つの事項に限定されている点も押さえておきましょう。
秘密の記号の記入禁止事項
- 国籍
- 信条
- 社会的身分
- 労働組合運動
上記以外の事項を通信して、労働者の就業の妨げになったとしても、本条違反にはなりません。
例として、「トラックやタクシー運転手の交通違反回数など」が挙げられます。
実務でも役立つ知識だと思いますので、押さえておきましょう。
また「あれ?この事項見たことあるなあ?」と思った方もいるでしょう。
法3条の均等待遇の規定でも、「労働組合運動以外」の事項の差別的取り扱いを禁止しています。
ごっちゃになりやすいので、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働条件編】」のコラムで、法3条の規定も確認しておくようにしましょう。

詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
まずは、無料のサンプルテキスト&講義動画で体験してみてください。