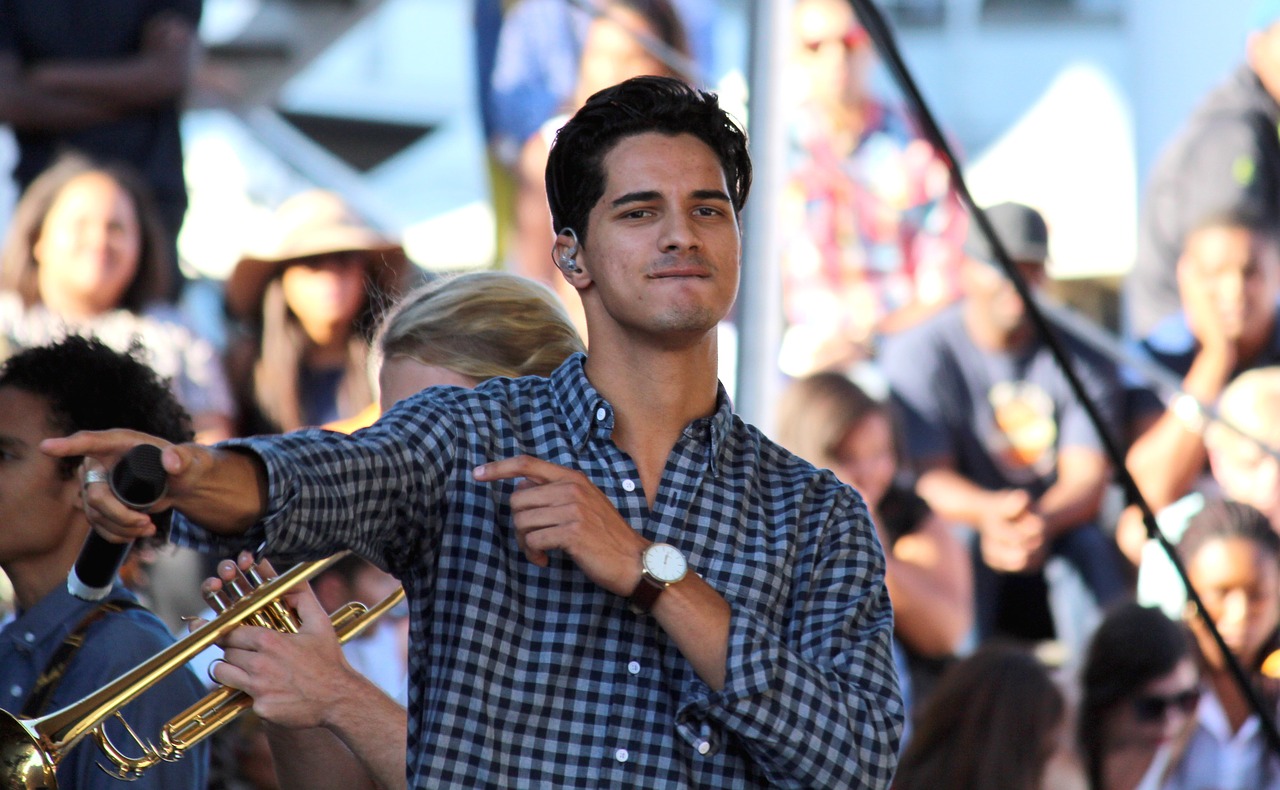【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【使用者編】
最近の社労士試験では、実務的な行政通達などが出題される傾向にあります。
そのためこちらの「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士である著者が、「アガルート速習カリキュラム」の内容を基に、実務的な知識をわかりやすく解説していきます。
初学者の方向けの内容になっていますので、ぜひご覧ください。
今回は「使用者編」となります。
社長でなくても使用者になり得る!?

労基法の条文では、「使用者は・・・」など、使用者に対して法律を遵守させる規定がされています。
そのため、「使用者の定義」を押さえることは、誰が責任の主体なのか判断する上で、重要になってきます。
労基法上の「使用者の定義」は、次のように規定されています。
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
わかりやすく、使用者に該当する者を分類したのが次の表です。
| 事業主 | 会社そのもの |
| 事業の経営担当者 | 社長や取締役などの経営者 |
| その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者 | 人事部長や営業課長などの現場責任者 |
この規定でいうところの「事業主」は、社長ではなく、法人のことを指すことになります。
「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは、人事や給与などの労働条件の決定や労務管理等について、一定の権限が与えらている現場責任者などが該当します。
ただ、役職だけ「人事部長」となっており、実質何の権限も与えられていないなどの場合は、「使用者」には該当しません。
あくまでも、形式ではなく、実態で判断することになっています。
また、「〇〇課長など」の中間管理職の社員は、部下に対して指揮命令する権限を与えられている場合、「使用者」という立場となります。
そして、その上司の「部長など」から指揮命令を受けている場合は、「労働者」という立場になるということもしっかり押さえておきましょう。
また、「出向」や「派遣」の場合、出向(派遣)先と元のどちらが、指揮命令関係にあるかで、「使用者」としての責任を負う立場にあるかが変わってきます。
表でまとめると次のようになります。
出向と派遣の取扱いまとめ
| 出向(派遣)元 | 出向(派遣)先 | |
|---|---|---|
| 在籍型出向 | 〇 | 〇 |
| 移籍型出向 | × | 〇 |
| 労働者派遣 | 〇 | △ |
労働者派遣に関しては、原則「派遣元」が労基法上の責任を負う立場にあります。
一部特例で「派遣先」が使用者として、労基法上の責任を負うケースがあることも覚えておいてください。
労基法上の義務を負う者(使用者)と保護を受ける者(労働者)を区別することができることで、労基法の理解が深まるので、しっかり押さえておきましょう。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!