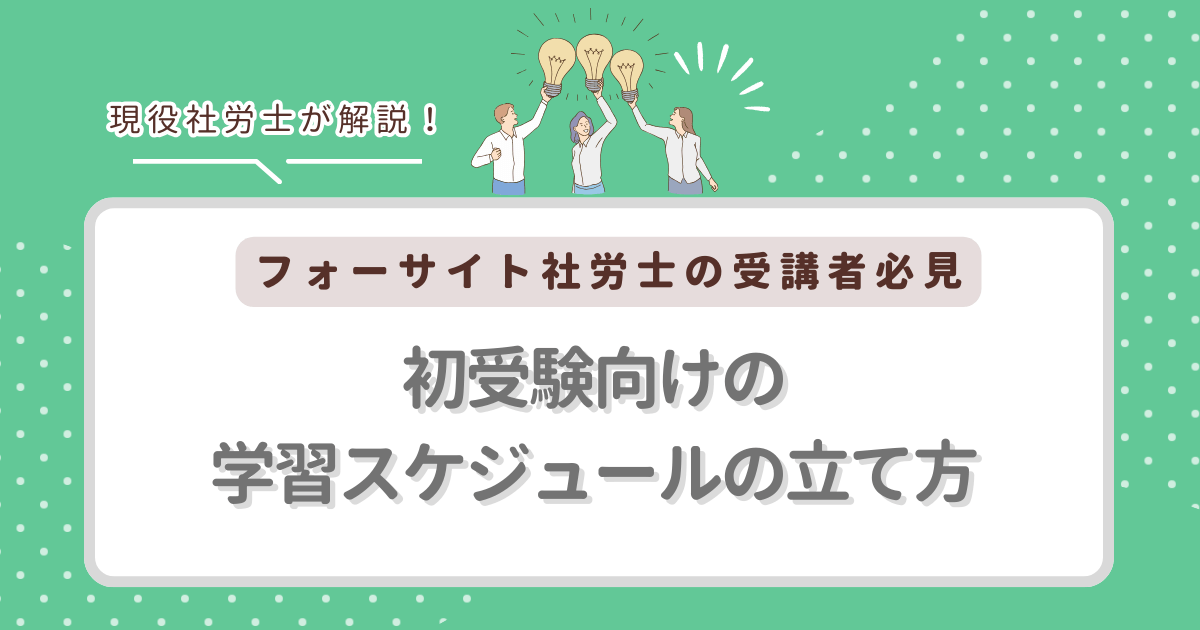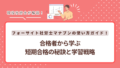【フォーサイト社労士の受講者必見】初受験向けの学習スケジュールの立て方
|
こういった悩みにお答えします。
私は、現在一般企業で働く現役の社労士です。
過去のフォーサイトの受講経験を基に、社労士試験までの最適な学習スケジュールの立て方を解説します。
本記事の内容
|
学習スケジュールを立てずに、いきなり勉強を始めるのはおすすめできません。
学習スケジュールを立てないのは、行ったことない場所に地図やナビ見ずに、目指すようなものです。
私も初受験の年に、学習スケジュールを立てず、いきなり勉強を始めて失敗した経験があります。
社労士試験のゴール(合格)までは、非常に険しい道のりです。
しっかりゴールまでの経路を逆算して、最短でのゴールを目指しましょう。
社労士試験までの学習スケジュールの立て方

学習スケジュールは、合格までの道のりを決めるものです。
安易に計画を立てると、達成できず挫折する原因になったり、思ったように成績が伸びないということにもなり兼ねません。
そうならないためにも、次の3つのことを意識して計画を立ててみてください。
|
1.本試験までの残り期間の確認
まず本試験までどのくらいの期間があるか確認しましょう。
社労士試験は、1000~1500時間ほどの学習時間が必要だと言われています。
なので理想を言えば1年以上の学習期間がほしいところです。
無理な計画は、受験の失敗に繋がりますので、余裕のある計画が立てることを心がけましょう。
学習計画を立てなかった受験生時代の私を反面教師にしてください。
私の受験生時代の失敗談が気になる方は、こちらの「【フォーサイト失敗談】社労士に不合格となった理由は?評判や価格、合格率を徹底分析!」をどうぞ。
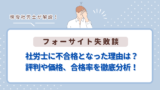
本試験前には、やらないといけない対策がたくさんあります。
例えば次のような対策が必要です。
|
これらを考慮すると、5、6月頃までには、10年分の過去問は、ある程度解けるレベルでないといけないということです。
そこから逆算して、各科目の「基礎講座」「過去問講座」「用語暗記」などを完了する学習スケジュールを組むようにしましょう。
2.生活スタイルの確認
普段フルタイムで働いている方にとって、学習時間の確保の仕方はとても大切です。
まずは現状の1日のスケジュールを紙に書き出してみてください。
《例》
| 〇平日 | 〇休日 |
|---|---|
|
|
このように普段の生活のタイムスケジュールを書き出したら、勉強に充てれそうな時間を計算していきます。
合格に必要な学習時間から逆算すると、最低でも次の勉強時間は確保したいところです。
| 〇1年 | 〇半年 |
|---|---|
|
|
学習期間が半年になると、初受験の方が独学や通常の通信講座で学習すると、合格ラインに達するのはほぼ不可能です。
それはほとんどの参考書が1年間以上の学習期間を想定しているものだからです。
その中でもフォーサイトは、初受験の方も十分合格が狙うことができる講座です。
実際に働きながら4ヶ月で合格した方もいます。
そのノウハウが気になる方は、下記からご確認ください。
「仕事が忙しくて、平日そんなに勉強できないよ!」という方は、次の時間も勉強時間に充てられないか検討してください。
|
意識すると、何気なく過ごしている時間も勉強時間になったりします。
特にSNSやLINEニュースなど、スマホを見られるような時間は勉強に充ててください。
3.アウトプット中心を意識
ここまで来たら、実際にどんな学習をするか決めていきます。
その前に次の格言を覚えておいてください。
| 過去問を制する者は社労士試験を制す |
基本テキストを読んで、インプットした量と点数は比例しません。
点数は、過去問を繰り返し解いたアウトプットの質と量に比例して、伸びていくものです。
インプットとアウトプットは、次の比率を意識してください。
| インプット:アウトプット = 3:7 |
つまり、インプットの倍アウトプットするということ。
裏を返せば、インプットをすればするほど、アウトプットの量も増やさないといけないので、その分だけ必要な学習時間も長くなってしまいます。
学習スケジュールも、アウトプットの学習を中心に予定を組むようにしてください。
「過去問ばっかりやってたら飽きて、途中で嫌になりそう」という方もいるでしょう。
フォーサイトでは、eラーニングシステム【ManaBun】によって、3種類のアウトプットが可能なので、初学者の方には特におすすめです。
またManaBunでは、自分のライフスタイルを入力すれば、学習スケジュールを自動で作成してくれる便利な機能もあります。
詳しくは、こちらの「フォーサイト社労士マナブンの使い方ガイド!合格者から学ぶ短期合格の秘訣と学習戦略」をどうぞ!
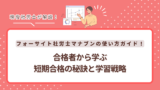
学習する上での注意点
一つ注意点として、計画を立ててから途中で変更するはやめましょう。
|
独学や通信講座だと、他の受験生の学習ペースなどがわからず、不安になると思います。
特に初受験だと、「全然成績が伸びないのは勉強の仕方が悪い」と、途中で計画を変更してしまいがちです。
その気持ちはグッとこらえて、自分のこれまでの努力を信じぬいてください。
実際に成績が伸びるのは、本試験の直前の人がほとんどです。
私もそうでした。
模擬試験の成績が悪くても、落ち込まないでください。
私も6月と7月の模擬試験では、合格ラインに全く達していませんでしたが、それから一気に成績が伸びた経験があります。
目標はあくまでも、「合格」であることを忘れないでください。
以上が学習計画の立て方を詳しく解説しました。
フォーサイトを初めて受講する方は、ここまでの内容に加え、教材がどのタイミングで届くのかも考慮しながら計画を立てるようにしましょう。
次章ではフォーサイトの教材の発送スケジュールを確認していきます。
フォーサイト社労士の教材発送スケジュール確認
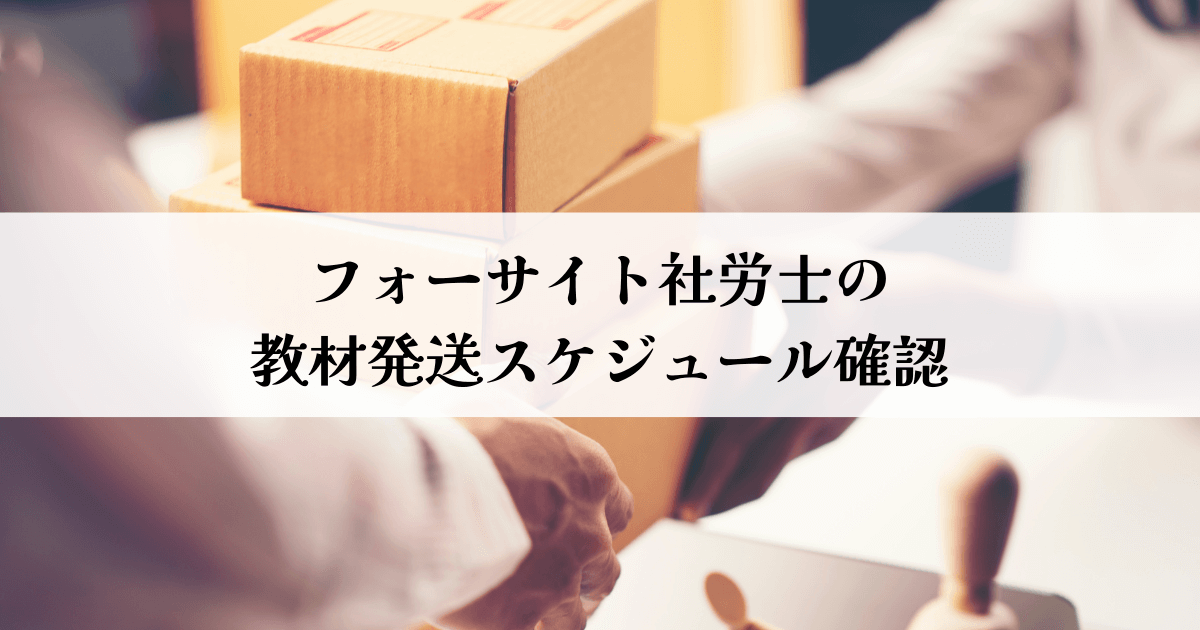
フォーサイト社労士講座の各科目の発送予定は、以下の通りです。
フォーサイト教材発送目安
| 科目 | 基礎講座 発送予定 | 過去問講座 発送予定 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 7月中旬 | 12月中旬 |
| 労働安全衛生法 | 7月下旬 | 12月中旬 |
| 労働者災害補償保険法 | 7月下旬 | 1月中旬 |
| 雇用保険法 | 10月中旬 | 2月上旬 |
| 労働保険徴収法 | 11月上旬 | 2月中旬 |
| 健康保険法 | 11月中旬 | 2月下旬 |
| 国民年金法 | 1月上旬 | 3月上旬 |
| 厚生年金保険法 | 1月下旬 | 3月中旬 |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 3月下旬 | 4月下旬 |
| 社会保険に関する一般常識 | 4月中旬 | 5月上旬 |
直前対策講座発送目安
| 科目 | 発送予定 |
|---|---|
| 法改正対策編 | 7月下旬 |
| 横断まとめ編 | 7月下旬 |
| 択一対策編 | 7月下旬 |
| 選択対策編 | 7月下旬 |
| 白書・統計対策編 | 7月下旬 |
その他発送目安
| 科目 | 発送予定 |
|---|---|
| 予想問題集(選択式) | 6月下旬 |
| 予想問題集(択一式) | 6月下旬 |
| 模擬試験 | 7月下旬 |
バリューセットによって、セット内容が異なりますので、まずフォーサイト公式サイトをご確認ください。
「バリューセットって何?」という方は、こちらの「フォーサイト社労士バリューセットの選び方ガイド!最短合格への最適コースを見つけよう」で詳細を解説しています。
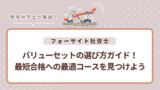
発送スケジュールを見て、以下のことがわかるかと思います。
|
「やることが多くて、なんだか不安になってきた」という方は、こちらの「【社労士一発合格の秘訣!】失敗から学んだ初心者でも実現可能な勉強法と試験対策」をご覧ください。
社労士試験が一発合格できる理由や勉強法について、詳しく解説しています。
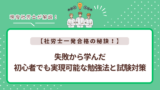
ここまで「学習スケジュールの立て方」について学び、「フォーサイトの発送スケジュール」を確認することができました。
それを踏まえて、「1年間」と「半年間」の理想の学習スケジュールを見ていきましょう。
【参考】1年計画と半年計画の学習スケジュール
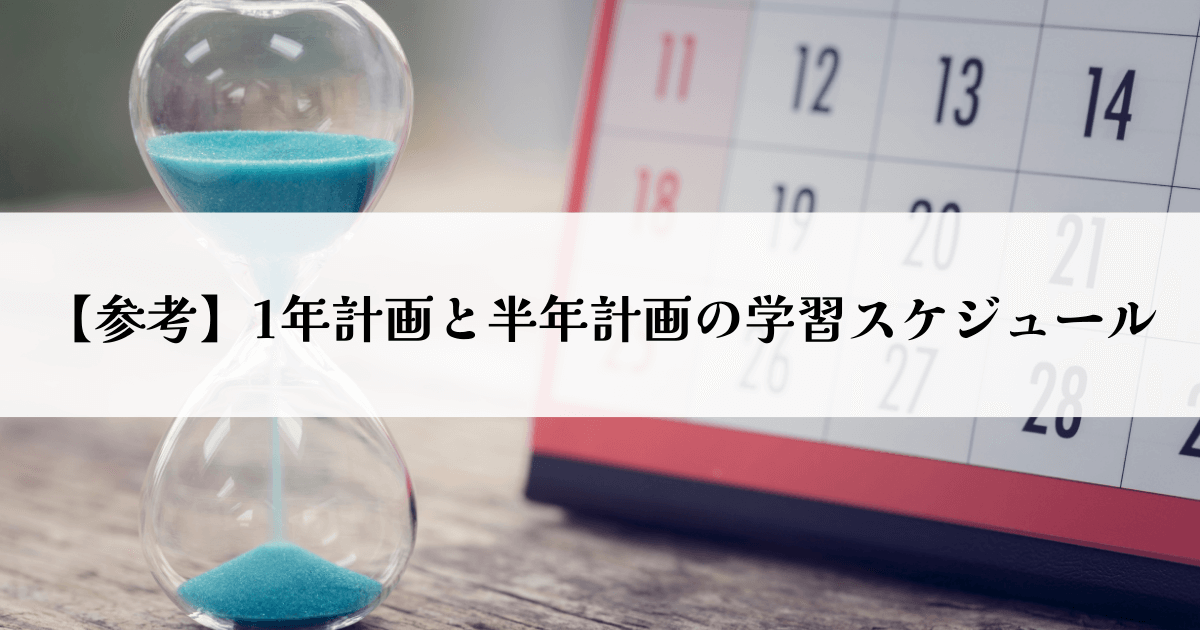
| 〇1年スケジュール | ||
|---|---|---|
| 期間 | 学習科目 | 学習内容・対策 |
| 9~10月 |
|
|
| 11~12月 |
|
|
|
|
|
| 1~3月 |
|
|
|
|
|
| 4~5月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6~7月 |
|
|
| 8月 |
|
|
以上が1年間の本試験までのスケジュールになります。
計画通りに進めるには、短期的な計画を立てることをおすすめします。
こちらを参考に、1日・1週間の学習スケジュールを立ててみてください。
続いては、学習期間が半年の場合の学習スケジュールです。
相当タイトなスケジュールになっています。
遊ぶ時間や趣味のための時間などはないと思ってください。
半年ぐらいなら我慢できるという方のみご覧ください。
| 〇半年スケジュール | ||
|---|---|---|
| 期間 | 学習科目 | 学習内容・対策 |
| 2~4月 |
|
|
| 5~6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7~8月 |
|
|
学習期間が半年以内となると、特にアウトプット優先の意識を忘れないでください。
「社労士試験って6ヵ月で合格できるの?」と思われている方は、こちらの「フォーサイト社労士講座の経験者が語る【一発合格できるテキストの秘密】」をご覧ください。
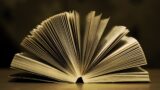
学習期間が1年・半年に係らず、学習を始める前に必ず学習スケジュールを立てるようにしてください。
どんなことでも事前準備で、結果が大きく変わるのです。
社労士学習スケジュール立て方まとめ
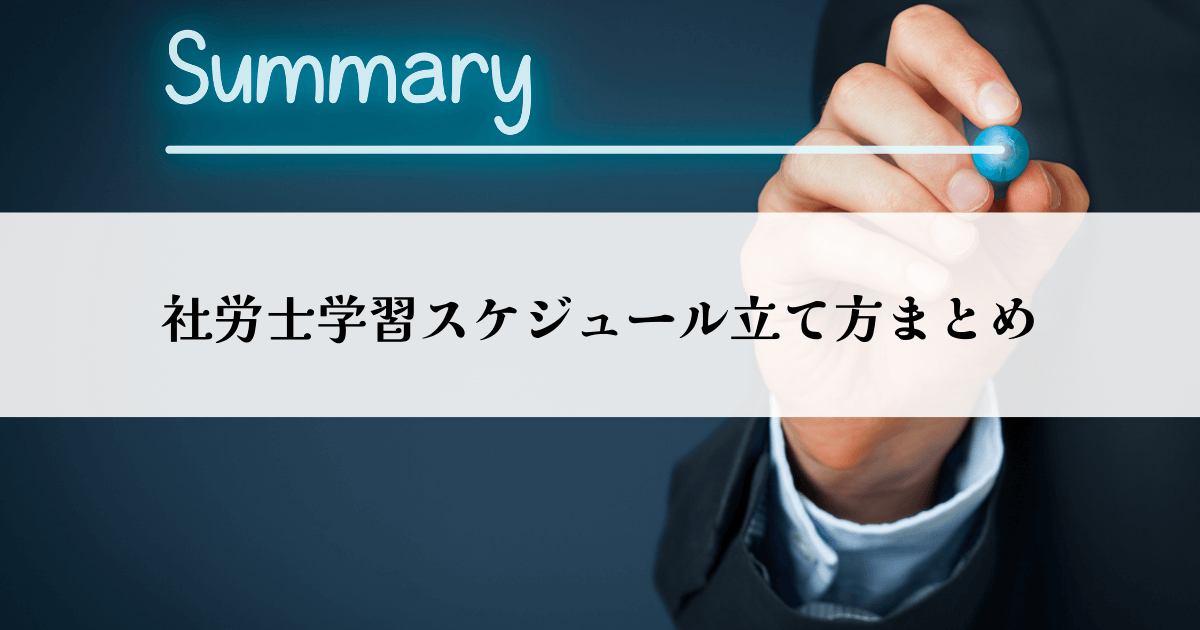
|