【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【労働契約編第2章】
社労士を目指す方の中にも、合格後すぐに独立開業しようと思っている方も少なくないと思います。
そのためには、実務的な知識もしっかり押さえておくと、同じタイミングで独立開業した方に比べ、大きなアドバンテージになります。
こちらの「ヤムチャ総務課長ブログ」では、現役の社労士である著者が「アガルート社労士講座」を受講して、実務に役立つ知識を解説するブログです。
受験勉強しながら即戦力となる知識を一緒に学んで行きましょう。
今回は、前回に引き続き「労働契約編」になります。
労働契約の期間には上限があるのか?
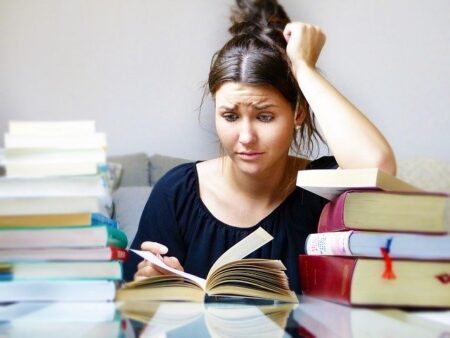
労働契約には、長期期間に渡る契約による人身拘束の弊害を排除するため、原則3年に制限されています。
ただし、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもについては、3年を超えることが可能。
また労基法14条に定める次の各号のいずれかに該当する労働契約は、特例として5年と規定されています。
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
ちなみに「自分の雇用契約書は、3年とも5年とも書いてないんだけど、有効な契約なの?」という方もいるかもしれませんが、こちらの制限は、有期契約に関するものです。
正社員で雇用されている方など「期間の定めのない労働契約」については、労働者がいつでも解約することができるため、契約は有効というわけです。
また試用期間という形で、期限を設けて労働契約を締結する場合がありますが、こちらはあくまでも正社員での採用を前提とした、適性や能力を判断する様子見期間という位置付けです。
そのため、使用目的で有期労働規約を締結することは認められません。
こちらに関連する判例として、「神戸弘陵学園事件」を確認しておいてください。
《参考元》労働基準判例検索-全情報
またここで問題となるのが、有期労働契約の場合、労働者は期間内に退職することはできないのかという点です。
続いては、「労働契約の解約」について解説していきましょう。
期間を定めた労働契約は、期間満了まで退職できない!?

「期間を定めのない労働契約」については、労働者側がいつでも解約できることは、先ほど解説しました。
「期間の定めのある労働契約」に関しては、労基法付則第137条で次のように規定されています。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
民法628条「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約を解除をすることができる。」の規定に関わらず、契約から1年を経過していれば、労働者はいつでも退職することができます。
ただし、こちらは労働者からの解約に関する規定であり、使用者側にもいつでも解雇することを認めたものではありません。
使用者は、次の労働契約法の規定が適用されるからです。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
使用者が、1年を超えて継続勤務している者との契約を更新しないこととする場合は、少なくとも契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
これを「解雇予告」と言います。
「解雇予告ってなに?」という方は、こちらの「【アガルート社労士講座|労働基準法】実務に役立つ基礎知識コラム【解雇予告編】」で詳しく解説していますので、よろしければどうぞ。

また、労働者側が退職する際、退職届を2週間前までに提出しないといけないと聞いたことがある方が多いと思います。
それは民法第627条の規定からきています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
「うちの会社の就業規則で、30日前までに提出って規定されているだけど・・・」という方もいるかもしれません。
どちらの規定を優先すべきかは、見解が分かれるところですが、個人的には「就業規則」の規定を優先すべきだと考えております。
その理由は、退職するまでは当然まだその会社の社員であり、社会人として社内ルールを遵守すべきだからです。
ただ、次のような場合は、例外だと思います。
- 「3か月前までに申し出ること」など、無駄に長い期間拘束されそうなとき
- 会社が法律を守らないブラック企業である
- 身体的または精神的に限界であるとき
ここまでして守る必要はありません。
期間も30日以上前の申告が規定されている場合は、会社側に交渉すべきでしょう。
今回は、「労働契約」の期限について解説しました。
実務でも必須の知識なので、しっかり押さえておきましょう。
詳細な内容は、「アガルート社労士講座」の各種カリキュラムで学ぶことができます。
アガルート社労士講座の詳細は、こちらの「アガルート社労士講座の評判・口コミは?【受講経験者が講座の全容を解明】」を参考にどうぞ!




